作業療法士の専門学校での勉強は難しい?入試から授業、国家試験まで徹底解説
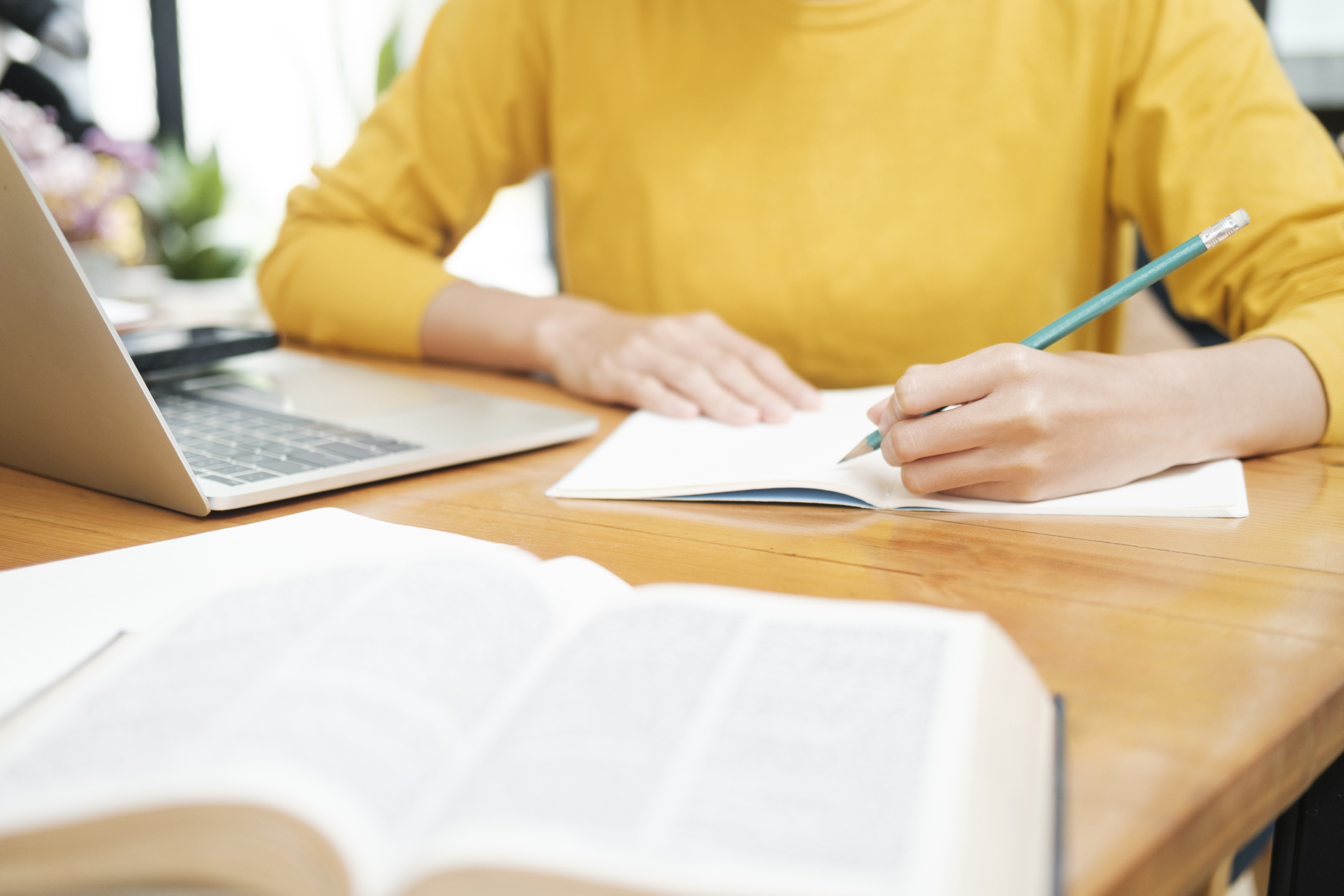
作業療法士の専門学校に進学したいけれど、「授業についていけるのかな」「国家試験までたどり着けるのだろうか」と不安に感じていませんか。医療系の学習は専門的で実習も多いため、進学前は誰でも少し身構えてしまうものです。
この記事では、作業療法士の専門学校で「勉強が難しい」と言われる理由や、入学から卒業までの学習の流れ、さらに不安を乗り越えるための具体的なポイントを紹介します。進学前の心構えを知ることで、安心して一歩を踏み出せるようになります。
この記事でわかること
・作業療法士の専門学校の入学・授業と国家試験の難易度
・学生が「難しい」と感じる3つの理由
・学習や実習を乗り越えるための具体的な対策
作業療法士の勉強が難しいと感じる理由
作業療法士の専門学校は、通い始めてから「思ったより大変」と感じる学生は少なくありません。その理由は、医療系専門職ならではの学習や生活リズムの変化にあります。

医療系ならではの専門知識と実習の負担
作業療法士の学習内容は、一般的な学校に比べて圧倒的に専門的で学習範囲が広いのが特徴です。
・解剖学・生理学などの基礎医学
・作業療法評価学・治療学などの専門科目
・精神障害、小児発達、高齢者リハビリなどの臨床領域
さらに、学内学習だけでなく病院や施設での臨床実習もあります。実習は1回あたり3〜8週間に及ぶこともあり、実習日誌・レポート・ケース発表などの課題も行わなければなりません。特に、患者さんとのコミュニケーションや評価実習で緊張する学生は多く、ここで「難しい」と実感します。
時間管理と勉強習慣が求められる生活
学校生活は、授業・課題・実習準備などが充実しています。通常は放課後のサークル活動やアルバイトを自由にすることもできますが、定期試験期間が近づいてくると勉強に集中する時間をしっかりと作ることが必要になります。
自分の時間と勉強する時間を作り、メリハリのある生活を送ることで、その分だけ学びの密度が高く充実した日々を過ごすことができます。
その結果として、学んだことがそのまま将来の仕事に直結する実感があり、やりがいを感じられます。計画的に学習を進めれば、1日ごとに自分の成長を感じられるでしょう。
実技・実習評価でのプレッシャー
作業療法士は、知識だけでなく実技能力や臨床判断力も問われます。そのため、実技試験・口頭試問・実習評価などで緊張感が強いのも特徴です。
例えば、作業療法評価の授業では、患者役のクラスメイトに対して関節可動域測定や筋力テストを実施し、手技の正確さを評価されます。また、実習では指導者が患者対応を直接チェックするため、精神的にプレッシャーを感じやすいです。
このように、知識と実技の両面で高いレベルを求められることが、「難しい」と感じる一因になっています。
作業療法士の勉強は本当に難しい?
作業療法士の専門学校や大学は、「入るのも大変そう」「授業についていけるか不安」という声がよく聞かれます。しかし実際には、入学から卒業までの難易度は人によって感じ方が異なります。
ここでは、入試のハードル、学習内容のボリューム、国家試験までの流れを具体的に解説します。これを知ることで、自分に合った準備や心構えができます。

入学試験の難易度と倍率の実情
作業療法士の学校の入学試験は、医学部などにくらべるとそこまで極端に難しいものではありません。倍率は学校や地域によりますが、1.2〜3倍程度が一般的です。
つまり、入学のハードルは「非常に高い」とは言えません。ただし、AO入試や推薦入試では「やる気・適性」を重視されるため、医療職を志す理由や将来像を明確に伝えることできるかどうかが合格のカギになります。
授業内容と学習ボリュームの特徴
入学後に難しいと感じるのは、授業で扱う内容の専門性です。作業療法士は、身体障害・発達障害・精神障害など幅広い分野に対応するため、解剖学・生理学・心理学などの基礎医学の他にも作業療法評価学・治療学など多くの科目を学びます。
1年次は基礎科目が中心ですが、2年次は専門性の高い授業や実技授業が増え、3年次には主に長期臨床実習と国家試験対策を行います。実習や症例研究が増えていきます。結果として、高校までよりも勉強時間は増える傾向にあります。
国家試験合格までに必要な勉強量
作業療法士になるには、卒業後に作業療法士国家試験に合格する必要があり、その合格率は約80〜85%前後です。(ちなみに、専門学校社会医学技術学院は、3年連続で国家試験合格率は100%です)
国家試験は、基礎医学から臨床実習で学んだ知識まで幅広く出題されるため、3年間で学んだ内容を総復習する力が必要です。 そのため、多くの学生は3年次の後半からは朝から夜まで国家試験対策の勉強を行い、模試や過去問演習で実力を固めています。
難しさを乗り越えるためのポイント
作業療法士の勉強は確かに学習量も多く、実習や国家試験に向けてハードな時期があります。しかし、適切な準備と学習方法を身につければ、無理なく卒業し国家資格取得まで到達することができるでしょう。ここでは、入学前から卒業まで意識したいポイントを紹介します。
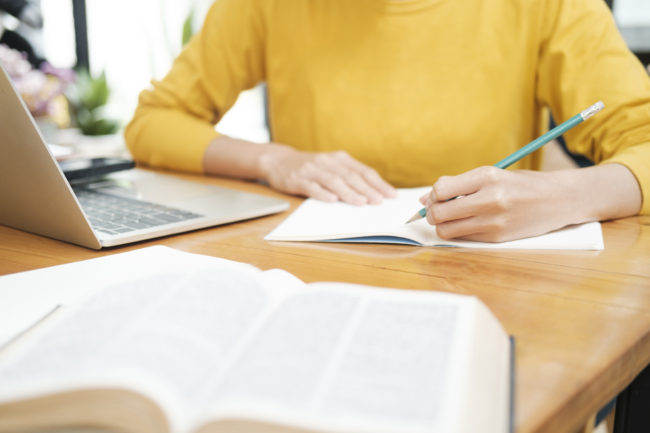
入学前に身につけたい基礎学力と学習習慣
作業療法士の専門学校に入学する時点で高度な医療知識は必要ありませんが、高校レベルの基礎学力はしっかり押さえておきたいところです。
特に必要になるのは以下の科目です。
・生物・化学 → 解剖学・生理学の理解に直結
・数学の基礎 → 統計や測定データの扱いに必須
・国語力 → レポート作成や国家試験の文章理解に必要
また、入学前(高校時代)から毎日30分〜1時間の学習習慣をつけておくと、入学後に急な課題や試験に対応しやすくなります。
実習や国家試験に向けた効果的な勉強法
学習負担が大きくても、正しい勉強法を身につけることで効率は大きく変わります。おすすめは次のようなステップです。
授業で学んだ内容を当日中に復習
↓
過去問・小テストで知識を定着
↓
実技や評価はペア練習で感覚を覚える
特に国家試験対策は、3年次の夏から過去問演習を開始すると余裕を持って仕上げられます。模試やグループ学習も活用すると理解が深まります。
仲間・教員との連携でモチベーションを保つ方法 専門学校生活は、個人の努力だけでなく仲間との協力が大きな支えになります。例えば以下の方法で学習効率やモチベーションを維持できます。
・授業後に短時間の勉強会や過去問解説会を行う
・実習前は先輩や教員に質問し、不安を解消する
・苦手分野を分担してまとめ、グループで情報共有
こうした環境を作ることで、孤独な勉強からチーム学習へ変わり、挫折しにくくなります。その為には、少人数で手厚いサポートが受けられる学校に進学することが、作業療法士の国家資格を取得するためにとても重要になると考えることが出来ます。
まとめ
作業療法士の専門学校は、入学自体は極端に難しいわけではありません。しかし、入学後の学習量・実習負担・国家試験対策の3つが大きなハードルとなり、多くの学生が途中で「思った以上に大変」と感じます。
ただし、事前に高校基礎の学力と学習習慣を整え、入学後は効率的な復習・実習準備・仲間との協力を徹底すれば、卒業・国家資格取得は十分に可能です。
作業療法士は患者さんの生活を支え、社会貢献度も高い仕事です。学校生活で得た知識と経験は、そのまま将来の実践力につながります。
もし今、「難しそうで不安」と感じているなら、この記事で紹介した学習習慣や対策について、今日から少しずつ取り入れてみましょう。努力した分だけ確実に未来の自信になります。

